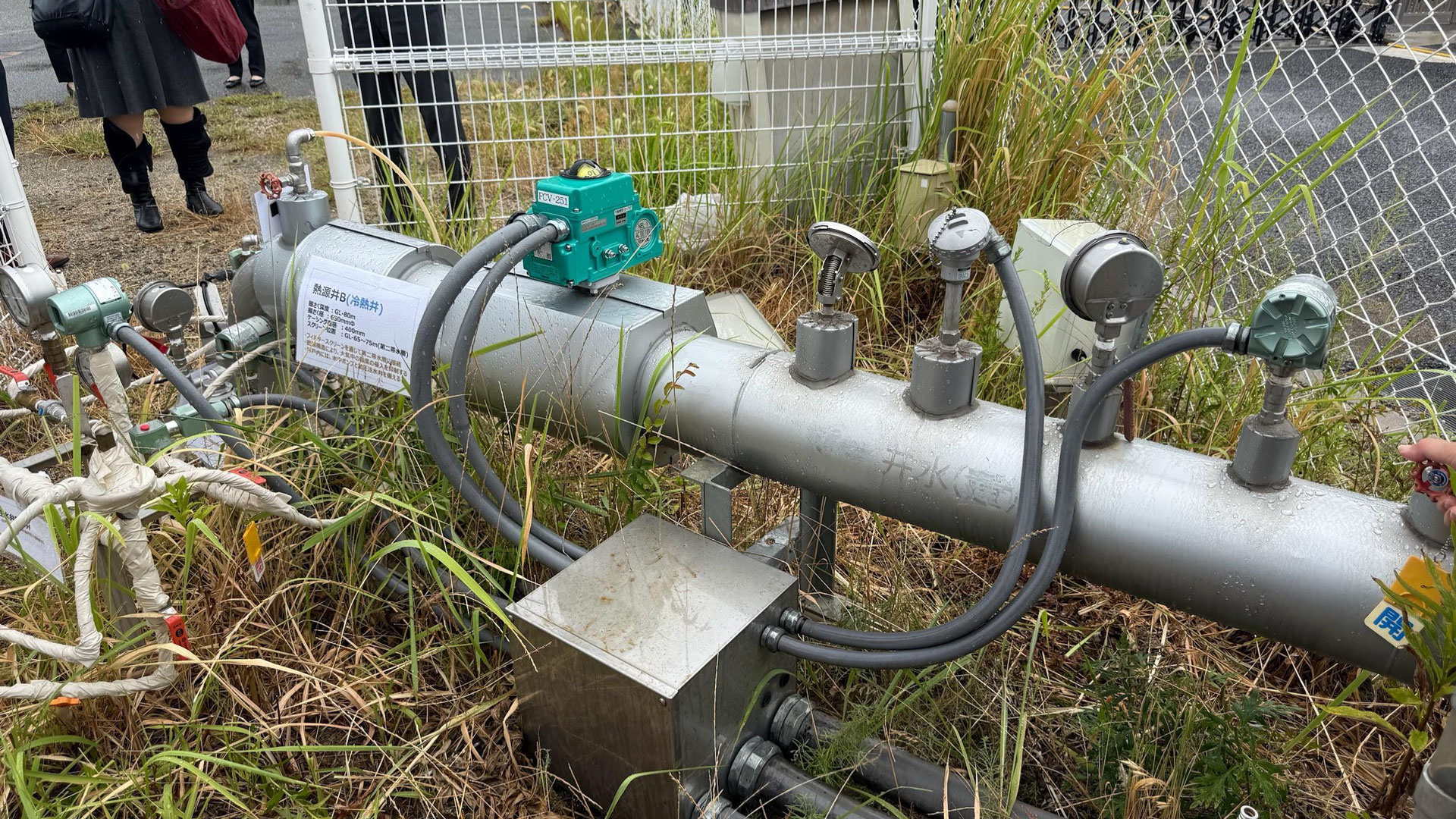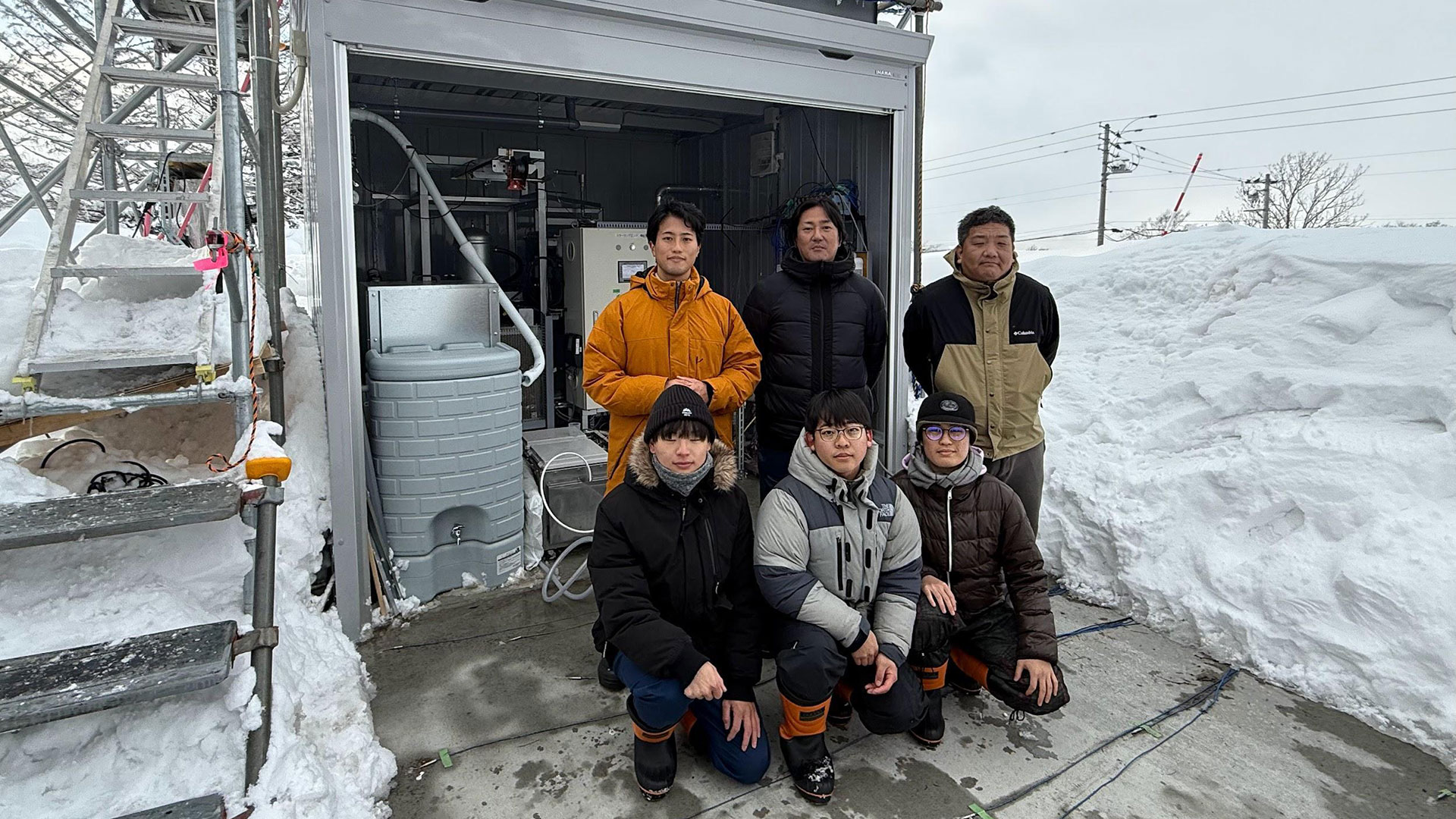写真)海底ケーブル(イメージ)
出典)Serg Myshkovsky/GettyImages
- まとめ
-
- 日本はカーボンニュートラル達成のため、北海道などの再生可能エネルギーのさらなる活用を目指している。
- 北海道から本州への電力輸送には、海底送電線が検討されているが、電気運搬船という選択もある。
- それぞれに利点と課題があり、最適な組み合わせが重要となる。
日本の2050年カーボンニュートラル目標達成には、再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠だ。中でも北海道は、広大な土地と優れた風況に恵まれ、陸上・洋上を問わず風力発電の巨大なポテンシャルを秘めている。その潜在量は、北海道一地域では消費しきれないほどであり、この「余剰電力」を電力需要の大きい本州、特に首都圏へ供給することができれば、日本の再生可能エネルギー比率向上に大きく貢献する。
また、地域偏在性の大きい再生可能エネルギーを広域で融通することは、電力系統全体の安定化やレジリエンス(強靭性)向上にも繋がる。特定の地域が悪天候で発電量が落ち込んでも、他の地域から電力を補うことができれば、より安定した電力供給が可能となる。北海道と本州を結ぶ電力の「大動脈」は、日本のエネルギー安全保障上も極めて重要な意味を持つ。
海底直流送電ケーブル計画
北海道と本州を結ぶ電力連系は、すでに存在する北本連系線(60万kW+30万kWの計90万kW)があるが、北海道のポテンシャルを最大限に活かすには容量不足が指摘されてきた。そうしたなか、海底直流送電ケーブルの新設計画が具体化しつつある。

この「北海道・本州間海底直流送電」プロジェクトは、工期6~10年程度、工事費1.5~1.8兆円程度がかかることが想定されていることから、送電事業のライセンスを取得したSPC(特別目的会社)を組成し、プロジェクトファイナンスによる資金調達することが検討されてきた。(資源エネルギー庁「電力ネットワークの次世代化について」)
しかし、工事費が巨額になることから、電力の安定供給を担う司令塔として、電気の需給状況の監視や電力会社間の電力融通の円滑化などを目的に設立された、認可法人電力広域的運営推進機関は、このプロジェクトを担うSPCなどが対象になり得る貸付制度を発表した。この制度は、電力系統の強化と再生可能エネルギー拡大を加速し、地域間電力融通と安定供給を確保することに貢献するものと思われる。
海底直流送電ケーブルの課題
一方、海底直流送電ケーブル計画にはいくつか課題がある。
-
環境への影響と漁業との共存:
長大な海底直流送電ケーブルの敷設は、海洋生態系への影響が懸念される。詳細な環境アセスメントと、影響を最小限に抑えるための工法選定、そして海域の先行利用者(地元漁業関係者など)との丁寧な合意形成が求められる。 -
技術的難易度と維持管理:
高電圧直流海底直流送電ケーブルの敷設・運用・保守は、高度な技術とノウハウを要する。特に、地震や津波といった日本の自然災害リスクを考慮した設計・対策が求められる。 -
コスト負担と電気料金への影響:
公的保証がついても、最終的なコストは電気料金を通じて国民が負担することになる可能性がある。費用対効果の十分な検証と、国民への透明性の高い情報公開が重要だ。 -
建設期間の長期化リスク:
関係各所との調整や許認可手続き、技術的課題の克服などにより、プロジェクトが長期化するリスクも考慮する必要がある。
もう一つの選択肢:電気運搬船
こうした固定インフラである海底直流送電ケーブルの課題を補完、あるいは代替する可能性を秘めているのが、株式会社パワーエックス(PowerX)が開発を進めている「電気運搬船(Power ARK)」である。(「『電気を運ぶ船』実用化に向け発進」2023.10.03)この構想は、船に大容量の蓄電池を搭載し、発電地と消費地の間を物理的に往来して電力を輸送するという革新的なアイデアである。

出典)Power X
電気運搬船の主なメリットは以下のとおりだ。
-
初期投資の柔軟性:
海底直流送電ケーブルのような巨額な初期投資が不要で、需要に応じて船の数を増減させるなど、段階的な投資が可能。 -
ルートの柔軟性と拡張性:
固定されたルートに縛られず、複数の港を結ぶことができる。新たな発電拠点や需要地にも対応しやすい。 -
災害時のレジリエンス向上:
地震などで陸上送電網が寸断された場合でも、被災地へ電力を緊急輸送する手段となり得る。 -
需給調整機能:
電力系統の状況に応じて充放電場所やタイミングを調整することで、系統安定化にも貢献できる可能性がある。
その電気運搬船「Power ARK」は、実用化に向けて着々と歩みを進めている。まず「Power ARK」の心臓部である蓄電池モジュールと関連システムの開発・生産は、岡山県玉野市の自社工場「Power Base」で行っている。

出典)Power X
電気運搬船そのものの建造に関しては、建造量日本一の今治造船株式会社と2021年12月に資本業務提携契約を締結。今治造船からの10億円の出資を受け、船舶用畜電池の開発・製造と、「Power ARK」のプロトタイプ船を2025年末までに共同で開発・建造し、2026年後半の商業運航開始を目指している。この提携では、パワーエックスが開発した船舶用畜電池を今治造船が建造する船体に搭載・組み立てる計画であり、専門性の高い造船技術と蓄電池技術を組み合わせることで、世界初の電気運搬船の実現を目指す体制を構築している。
2024年4月には、電気運搬船を開発・販売する新会社「海上パワーグリッド」を設立した。同時に電気運搬船よりコストを抑えられ、短距離で平水海域に適したバージ型電気運搬船「Power Barge」を発表した。

出典)Power X
この船は、バージ、いわゆる「はしけ」型であり推進機関を持たないため、電気運搬船「Power Ark 100」よりも建造費が安くすむ。水深が深く、波の荒い海域では電気運搬船、穏やかな海域ではバージ型電気運搬船、と使い分ける予定だ。例えば瀬戸内海などの内海を想定している。その機動性の高さから、例えば災害時など、被災地にいち早く電力を届けることができる。

出典) Power X
このように可能性が広がる電気運搬船だが、本格的に普及するためにはいくつかの課題を解決しなければならない。
-
蓄電池の性能とコスト:
電池の性能は日進月歩だ。大量の電力を効率よく輸送するためには、エネルギー密度が高く、長寿命で、かつ低コストな蓄電池の開発が不可欠である。安全性確保も重要課題だ。 -
充放電インフラの整備:
港湾における大規模な充放電設備の整備が必要となる。そのコストが課題だ。 -
経済性と運航効率:
燃料費や人件費を含む運航コスト、気象条件による運航の安定性など、経済合理性を確立する必要がある。 -
関連法規や安全基準の整備:
新しいコンセプトの船舶であるため、国際的なルール作りや安全基準の策定も求められる。
これらの課題の内、「充放電インフラの整備」だが、パワーエックスは、2060年まで世界で1,000基以上の火力発電所が廃止される見込みなことから、これら既存インフラを電気運搬船の充放電地点として再利用することが可能だとしている。
海底直流送電ケーブルと電気運搬船。どちらか一方の選択肢に固執するのではなく、それぞれの特性を理解し、日本の地理的条件やエネルギー事情に合わせて最適に組み合わせる視点も必要だ。資金調達の面では、経済合理性と実用化の時期も重要な要件となる。
海底直流送電ケーブルという「動脈」と、電気運搬船という「毛細血管」のような柔軟な輸送手段が連携することで、より強靭で効率的なエネルギー供給体制が構築できるかもしれない。これらの壮大なプロジェクトは、技術開発、資金調達、社会受容性の確保など、多岐にわたる挑戦を伴う。官民一体となった取り組みと、絶え間ない技術革新が望まれる。





Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載
- テクノロジーが拓く未来の暮らし
- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。